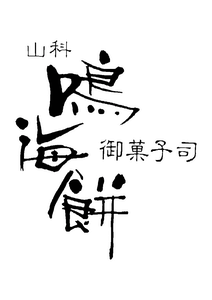どうも、新人ちゃんです!
前回のブログは3月3日のひな祭り、女の子の健やかな成長を願いお祝いする日についてでした。
今回は5月5日の端午の節句、男の子の健やか な成長を願う日について調べていきます!!

まずは柏餅です。
端午の節句に柏餅を食べる風習は、江戸時代に日本で生まれました。柏は、新芽が出るまで古い葉が落ちないことから、家系が続く縁起物とされました。古くから縁起担ぎのめでたい木と言われているため神事に欠かせない餅を縁起の良い柏の葉で包んだ柏餅を端午の節句に食べることにより、男の子が元気に育つ
ことを願っています。

次にちまきです。
ちまきを食べる風習は中国の古い歴史に由来します。
古代中国の楚(そ)という国の政治家・屈原(くつげん)が、国の行く末に絶望して5月5日に川へ身を投じて亡くなりました。人々が屈原を供養するために川にちまきを流していたことが起源だそうです。こちらは少し重たい話でした・・・。
柏餅は主に関東で食べられ、ちまきは関西で食べられるみたいですが、当店では両方ご用意しておりますので是非ご賞味ください。
ここで新人ちゃんは疑問を抱きました・・・。
5月5日の祝日は「子どもの日」とされています。端午の節句と子どもの日は何が違うのでしょうか?
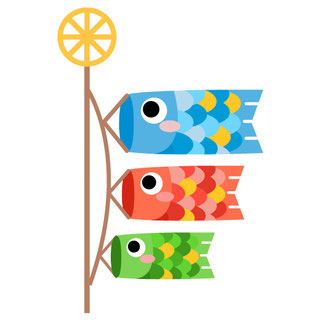
子どもの日は1948年に、5月5日を「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」お休みの日と決められてから、端午の節句の日に由来してこどもの日になったそうです。
端午の節句は男児の健やかな成長を願い、子どもの日は男女を問わずにお祝いし、子どもの健やかな成長を願うという違いがあるみたいです。
ではでは皆様、素敵なGWをお過ごしください!!